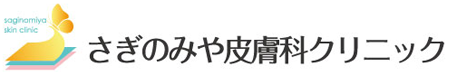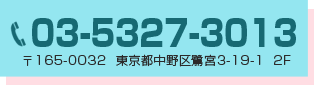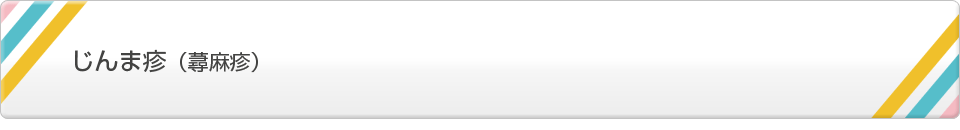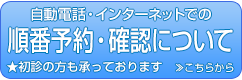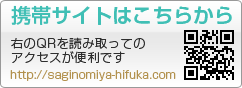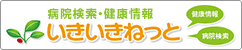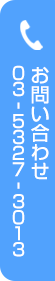“じんま疹”という名前は誰でも聞いたことがあると思いますし、今までじんま疹を経験されたことがある人も多いのではないかと思います。ただ、受診される患者様の中には、湿疹などの他の皮膚疾患を“じんま疹”と思っていらっしゃる人や、「じんま疹といえばアレルギー」と思い込んでいらっしゃる人も多いように思います。
実はじんま疹といっても、その中にはいろいろな病型があり臨床症状や原因も異なります。(下記表)
Ⅲの血管性浮腫とⅣのじんま疹関連疾患はあまり一般的ではありませんので、ここではⅠの特発性じんま疹とⅡの刺激誘発型じんま疹について説明します。
| じんま疹の主たる病型 |
Ⅰ.特発性のじんま疹
|
Ⅱ.刺激誘発型のじんま疹(特定刺激ないし負荷により皮疹を誘発することができるじんま疹)
|
Ⅲ.血管性浮腫
|
Ⅳ.じんま疹関連疾患
|
日本皮膚科学会 蕁麻疹診療ガイドライン
まずⅠの特発性じんま疹ですが、実はこの病型が最も多くみられるもので、医療機関を受診するじんま疹全体の8割程度を占めます。
典型的症状は、明らかな原因もなく、ある時突然、境界がはっきりした円形や環状や不整な地図状のわずかに盛り上がった赤い斑が出現し、激しいかゆみを伴います。全身のどこにでも出てくる可能性があり、一度発症すると基本的にはその後毎日の様に出現します。
そして、最も特徴的なのは、これらの皮疹は通常数十分以内に跡形もなく消えてしまったり、場所が移動したりすることです。
例外を除いて1日以上同じ部位に持続して出現することはありません。これは他の皮膚疾患ではみられない特徴であり、じんま疹を鑑別する際の重要な情報になります。形式的に発症してからの症状が出ている期間が6週間以内のものを急性じんま疹、6週間以上経過したものを慢性じんま疹と呼んでいます。
次にⅡの刺激誘発型のじんま疹ですが、これらは特定の刺激や負荷により皮疹が出現するタイプです。その中でもアレルギー性じんま疹がおそらくみなさんが考えているじんま疹に近い病型ではないかと思いますが、実際にはじんま疹全体の数%を占める程度です。
特定の原因物質への曝露により、その数分から数時間後に特発性じんま疹と同様の皮疹が出現し、やはりしばらくすると治まってきます。原因物質への曝露がない限りは症状が出ることはありません。まれにアナフィラキシーといわれる血圧低下や気管支喘息発作や最重症のショック状態、また、食物が原因の場合では口腔粘膜の腫れや違和感、悪心、嘔吐、下痢、呼吸が苦しいなどの症状が出ることがあり、注意が必要です。
このケースでは、再び同じ原因物質に曝露すると同じ症状が起こるため、原因を特定することが重要で、それ以降は原因を回避する必要があります。
その他の病型のじんま疹の症状も原因や誘因が異なりますが、共通の症状として、「突然出現して、しばらくすると跡形もなく消えてしまう」というのが他の皮膚疾患とは異なる特徴です。
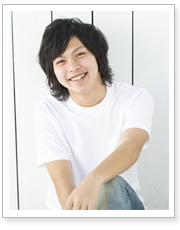
では、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。それはじんま疹の本態が皮膚表面そのものの炎症ではなく、皮膚表面(表皮)の下にある真皮といわれる層の上部で、毛細血管の拡張や、血管壁の透過性の亢進が起こり、血管内から血漿成分が漏れ出てきてその場に蓄積し、浮腫といわれる状態を形成したものだからです。
つまり、このたまった液体がまた血管内に戻って、血管の拡張もおさまると、跡形なく消えてしまうわけです。
では、どうして血管が拡張したり、透過性が亢進したりするのでしょうか。これには様々な化学伝達物質が関与していますが、その中でも最も重要なものはヒスタミンという物質です。
ヒスタミンは真皮内に存在している肥満細胞という細胞に何らかの刺激が加わったときに放出されます。この刺激を引き起こすものこそがじんま疹の原因といえるのですが、簡単に決定することができず、じんま疹診療ガイドラインでは表2のように直接的誘因と背景因子に分けて挙げられていて、これらが複合して病態形成に関与するものと考えられています。そして、これらの最も深く関わる因子によってじんま疹の病型が分類されることになります。
ここで病型別に考えてみます。まず、最も頻度の高いⅠの特発性じんま疹では残念ながらはっきりした直接的誘因がなく、感染、食物、疲労、ストレスなどが背景因子となり得ますが、いずれの因子も病態の全容を説明できるものではありません。
「原因は何ですか?」と尋ねる患者様が多いですが、「はっきりとした原因はわかりません。」と答えることになってしまうのです。
次に、Ⅱの刺激誘発型のじんま疹では特発性じんま疹とは異なり、原因として特定の刺激や負荷が存在します。アレルギー性じんま疹では、食べ物、薬物、植物、昆虫の毒素など症例によって異なりますが、基本的には原因物質の曝露の数分後から30分以内に発症することが多いため、患者様自身がある程度原因を特定できることが多いと思われます。このケースの発症メカニズムは以前より詳細に研究されており、“Ⅰ型アレルギー反応(即時型アレルギー反応)”といわれます。
先程出てきた肥満細胞の表面にはIgEという抗体の一種がくっついており、原因物質がこのIgEと結合するとヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、その後の一連の反応が起こるというものです。
その他の病型として、例えば物理性じんま疹では皮膚表面の機械的擦過、寒冷曝露、日光照射、温熱負荷、圧迫、水との接触、振動などの刺激が原因となり、食物依存性運動誘発アナフィラキシーでは特定の食物摂取+運動負荷が原因となり、コリン性じんま疹では入浴、運動、精神的緊張など発汗ないし発汗を促す刺激が原因となります。
以前はⅠ型アレルギー反応がじんま疹の主なメカニズムであると思われていましたが、近年はIgEを介したⅠ型アレルギーが原因となるじんま疹は実際にはそれほど多くないと考えられています。
| じんま疹の病態に関与する因子 |
1. 直接的誘因(主として外因性、一過性)
|
2.背景因子(主として内因性、持続性)
|
日本皮膚科学会 じんま疹診療ガイドライン
まず、Ⅰの特発性じんま疹では明らかな原因が認められないために通常は特に検査も行いません。血液検査を希望する患者様が多いのですが、そこからじんま疹の原因に関する情報は得られないからです。当院でも通常のじんま疹に対しては、血液検査は行っておりません。ただ、難治性の慢性じんま疹では基礎疾患のスクリーニングのために行うこともあります。
次にⅡの刺激誘発型のじんま疹では、先ほど述べたように多くの場合その経過から原因を推測することが可能です。同じ刺激や負荷をもう一度与えて、症状が誘発されることを確認することで原因を確定することができますが、アナフィラキシー反応が起きるリスクもあるため有用とは言えず、必ずしも行うべきものではありません。
ここで、Ⅰ型アレルギーが関わっていると思われるアレルギー性じんま疹や接触じんま疹ではいくつかの比較的安全な検査方法があります。
まず1つは血液検査で血清中の各抗原に対する特異的IgEという抗体の量を測定するという(いわゆるアレルギー検査と呼ばれているもの)ものです。検査項目として、様々な抗原(ダニ、ハウスダスト、食品、花粉など…)があるため、調べたいものをピックアップしていただきますが、保険適用上13項目までとなります。便利なものとして、MAST36というものがあり、これは頻度的によく測定する36項目を一度に測定できるというものです。保険点数も13項目と同じですので、お得ということになります。
ただ、その結果の解釈は単純ではなく、食物が原因と思われる場合などで有用な場合もありますが、必ずしも値が高いからと言ってそれが原因であると断定することはできず、あくまでも参考になると考えたほうがいいと思います。
血液検査に比べて信頼度の高いものとして、抗原塗布試験、プリックテスト、スクラッチテスト、皮内反応といった一連の検査法があります。これらは実際に原因の可能性がある物質を皮膚にそのまま塗布したり、皮膚に少し傷をつけてから塗布したりして、その部位にじんま疹が誘発されるかどうかを見る検査です。比較的安全ではありますが、アナフィラキシー反応が起きる可能性が全くないとは言えず、慎重に行う必要があります。基本的にこれらの検査は当院では施行しておりません。

じんま疹の治療として、原因、悪化因子の除去や回避が基本であり、特に原因が明らかであるⅡの刺激誘発型のじんま疹では重要となります。
薬物療法としてはヒスタミンの作用をブロックする抗ヒスタミン薬の内服が中心となります。この薬剤はヒスタミンがヒスタミンH1受容体に結合することを阻害することで効果を発揮します。Ⅰの特発性じんま疹では、薬物療法を継続して病勢を鎮静化することが目標となります。
抗ヒスタミン薬にもいろいろ種類がありますが、第1世代と第2世代に分けられます。
第1世代はヒスタミンの作用のみを阻害しますが、第2世代はヒスタミン以外にも肥満細胞から様々な化学伝達物質が放出されるのを阻害する作用を併せもっていて、抗アレルギー薬とも呼ばれます。
一般的に抗ヒスタミン薬は中枢神経にも作用するために、副作用として鎮静作用、つまり眠くなるものが多いのですが、第2世代はこの点も改善されていて中枢への移行が少なくなっており、眠気の副作用が少なくなっています。
以上の点から、現在は第2世代が主流となっています。
ただ、抗ヒスタミン薬の効果は個人差があり、1種類の薬剤で効果が得られない場合は他の種類に変更したり、追加したり、投与量を増やしたりすることを行います。
抗ヒスタミン薬以外にもいくつか効果が期待できる内服薬はありますが、あくまでも補助的であると考えます。
症状が重いケースや抗アレルギー薬とそれ以外の補助的な内服薬を併用しても症状が治まらないケースでは、ステロイドの内服を行うこともあります。ただし、長期間の継続はお勧めできないため、一時的な使用にとどめる必要があります。
また、それでも治まりにくい重症例には抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤であるオマリズマブ(ゾレア®)の注射による治療を行っております。
なお、外用薬については、基本的に効果はあまり期待できず、通常は使用しません。
どれくらいの期間、内服を続けるかについては、特に決まりはありませんがまずは1~2週間程度内服をして症状が安定して出現しなくなれば一度内服を中止してみるか、減量または内服間隔をあけてみて経過を見ます。
再び症状が出てくる場合は元の内服方法に戻しますが、経過が良好の場合はさらに減量または内服間隔をあけます。これを繰り返して、3日に1回内服する程度で症状が出なくなったら、頓服に切り替えます。
特に慢性じんま疹では長期間内服が必要となることもあり、急がずにゆっくりと減量していくことが大切です。
予防に関しては、特発性じんま疹では通常必要はありませんが、アレルギー性じんま疹では原因があきらかなものに対しては原因の除去や回避が重要となってきます。
ただし、抗原を含む食品の誤食や昆虫毒の刺入など、原因の除去や回避が完全にできない可能性があります。
その場合はすぐに対処できるように抗アレルギー薬やステロイド内服薬をあらかじめ常備していただくこともあります。
ただし、薬物療法により抗原に対する過敏性そのものを改善したり、予防的に薬剤を内服することによって症状が出現することを完全に防ぐことはできませんので、過去にアナフィラキシー様の症状の既往のある場合や、呼吸苦などの症状が出現した場合は、直ちに救急施設のある病院を受診することをお勧めしています。